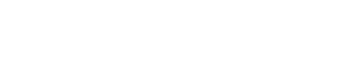中古物件の耐震基準を確認するには?建築物の耐震補強工事の種類

地震が起きたときに住む人の生命や財産が守られるように、一定規模の地震に耐えられる構造の建物が建築されるよう、住まいの耐震基準が定められています。
中古物件を購入するときには確認申請を受けた年月日を調べて必要に応じて耐震補強工事をする必要があります。
このページでは、建築の耐震基準、中古物件の耐震基準の確認方法、耐震補強工事の種類について解説します。
耐震基準とは
耐震基準は建設しようとする建築物に対し、国が最低限クリアすべき基準を規定した基準です。
耐震基準は大地震の教訓を生かして改正され続けています。
特に1981年に大幅に改正されたため、建築確認の日付が1981年5月31日以前は「旧耐震基準」、1981年6月1日以降は「新耐震基準」と呼ばれています。
新耐震基準と旧耐震基準の違い
では、新耐震基準と旧耐震基準は何が異なるのでしょうか。
中規模(震度5程度)の地震に対する基準
旧耐震基準では「建物の自重の20%に相当する地震力」に対して許容応力度計算を行い、構造材料の許容応力を上回らないようにする耐震設計が定められていました。
許容応力度とは、外部から力が加わった際にもで損傷を遺さずにもとに戻ることができる応力の限界値のことです。
これは、震度5程度の中規模地震の際に倒壊あるいは倒壊しないという位置づけの「一次設計」という概念です。
つまり、旧耐震基準では震度5強以上の地震についての規定がなく、さらに震度5程度の地震があった場合に建物は倒壊はしないものの大きな損傷を受けている可能性があるというものでした。
大規模(震度6以上)の地震に対する基準
1981年からの新耐震基準ではこれまで規定されていなかった震度6強~7程度の大規模地震で倒壊・倒壊しないことの検証を行うことが定められています。
新耐震基準で検証することを求めたこの部分を「二次設計」と呼びます。
耐震構造・制振構造・免震構造の違い
地震の揺れの対策となる構造には「耐震構造」「制振構造」「免震構造」があります。
それぞれの違いを見ていきましょう。
耐震構造
耐震構造は地震の揺れを受け止めて耐えられるよう建物自体を頑丈につくる構造です。
新耐震基準以降はすべての住宅が大地震に耐えられる前提で作られ、そのうち耐震構造は約99%を占めています。
耐震構造の住宅は大地震のとき、建物自体は大きく揺れるので、中にいる人も激しい揺れを感じます。
制振構造
制振構造は建物の壁や柱などにダンパーなどの制振装置を導入し、地震の揺れを吸収します。
ダンパーが地震で動き、地震の力をほかのエネルギーに変え、揺れを小さくします。
ダンパーにより地震の揺れを耐震構造の20~30%軽減できるため、建物のひび割れを軽減できます。
免震構造
免震構造は建物の基礎にゴム製などの免振装置を設置し、基礎が地震の揺れを吸収します。
大地震のときに建物が長くゆっくりと揺れることで、家具の倒壊や建物の損傷をある程度防ぐことができます。
免震構造は建築費用が3%程度アップするものの、地震の力を40~60%カットすることができるため、マンションなどでよく採用されています。
旧耐震基準の物件を購入する場合の確認事項
新旧耐震を確認する
新耐震基準は1981年に施行されましたが、1981年以降に完成した建物がすべて新耐震基準というわけではありません。
建物の建築の際には検査機関による建築確認を受ける必要があります。
そのため、建物がどの耐震基準に則して建築されたかは建築確認の申請日を確認すると分かります。
申請日の確認は「建築確認証」や「検査済証」にある建築確認申請日をチェックします。
耐震診断を受ける
新築住宅は地震に対する強度を計算したうえで建築されます。
しかし、強度の高い建物でも、年月を経て耐震強度は低下していきます。
そこで、中古住宅を購入する際は、建物の現状での耐震強度を知るために建物耐震診断を行います。
診断をして必要な場合には耐震補強工事を実施することで安心して住むことができます。
耐震補強工事の種類
耐震補強工事には「基礎の補強」「壁の補強」「屋根の軽量化」「結合部の補強」があります。
基礎の補強
基礎が劣化していると、強い地震が発生した際に建物が倒壊する可能性があるため、基礎の補強工事を行う必要があります。
地盤沈下などで基礎が埋没してしまっている場合、既存の基礎の上に新たに基礎を作ります。
建物をジャッキアップして持ち上げ、新たに基礎と土台をつくり、床下にコンクリートを打設して補強します。
しかし、この方法は隣地との間隔が狭いとできないため、現在ある基礎の側面に鉄筋で骨組みを行い、コンクリートを流し込んで新たに基礎を作り補強する方法もあります。
壁の補強
壁のバランスが悪い建物は新たな壁を作ったり、必要な場所に筋交や耐震金物の設置、構造用合板の設置などを行い、耐震補強する方法があります。
また、任意の部屋を耐震シェルター化する方法もあります。
部屋の中に耐震化された部屋を作るというイメージで、もしほかの部屋が崩落してもシェルター内は安全を確保できる、というものです。
屋根の軽量化
建物の上部を軽量化すると耐震性をアップさせることができます。
建物上部を軽くすることで、建物全体の重心が下がり耐震性が増加します。
瓦屋根は格式の高い外観の家を作ることができますが、屋根の重量が重くなるため、耐震性で見ると不利となります。
この場合、屋根材は化粧スレート、ガルバリウム鋼板、アスファルトシングルなど、軽量な屋根に葺き替えることで屋根を軽量化することができます。
*結合部の補強
地震力は建物の弱い場所の結合部に集中しますので耐震金物で補強が必要です。
筋交プレート、ホールダウン金物、アンカーボルトを結合箇所に適切に使用します。
旧耐震基準の建物は補強工事が必要
旧耐震基準で建築された建物は建築から少なくとも40年以上経過しているため、耐震補強工事が必要です。
耐震診断を受けることにより、耐震診断と耐震補強工事に対して地方自治体から補助金・助成金を受けられる場合もあります。
旧耐震基準の建物にお住いの方や中古住宅を検討する方は、まずは耐震診断を実施し、適切な補強工事をすることで、万が一のときの対策となります。
沖縄の型枠工事は、民間から公共までお任せください。
会社名:株式会社喜舎場組
住所:〒904-0304 沖縄県中頭郡読谷村楚辺2141-1
TEL:090-9785-0238
FAX:098-927-1589
営業時間・定休日:日曜